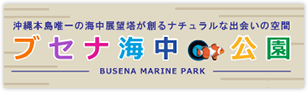- 「ブセナ海中公園」の
サンゴは今 - 第1期植付計画
- 第2期植付計画
- 第3期植付計画
- 第4期植付計画2024年度
実施予定


沖縄の美しい海を守りたい
ブセナ海中公園養殖サンゴ植付事業
1.「ブセナ海中公園」のサンゴは今…
ブセナ海中公園の位置する沖縄本島西海岸エリアは沖縄国定海岸公園に指定されています。その中でも特に海中景観の素晴らしさが認められ「海域公園地区」という特別区に指定されています。
ブセナ海中公園は1970年8月の開業以来、「沖縄の最も重要な観光資源である海の魅力を沖縄県民並びに国内外の観光客に伝え、またサンゴ礁をはじめとする自然環境の保全に努める」をキャッチフレーズとして、多くのお客様にご利用していただきました。
 2020.10撮影
2020.10撮影しかし、1980年代に発生したオニヒトデによる食害、地球温暖化に伴う海水温の上昇、河川からの赤土流入などにより、沖縄のサンゴ礁は壊滅的な被害を受けました。
ブセナ海中公園の海中展望塔やグラスボートから観察できるサンゴ類も減少しています。
サンゴ礁は沖縄の海で非常に重要な役割を担っています。
サンゴ礁に依存して生きている生物達は、サンゴが消滅すると消えてしまいます。魚類、貝類、甲殻類など、生物多様性に富んだ生態系の中心にいるのがサンゴです。
 2021.07撮影
2021.07撮影ブセナ海中公園の周辺海域では、ここ10年ほどの間にサンゴが復活しつつあります。
潮通しの良い海域では、以前のような健康状態の良いサンゴの群落があり、サンゴに依存する他の生物も観察できます。
しかし、少し離れた場所では荒涼とした何もない海底が広がっており、サンゴが生息していない場所では他の生物もあまり見られません。
- サンゴが密生している場所
-
 2020.10撮影
2020.10撮影
サンゴが密生している場所では、その他の生物も多い。
沖縄の海の特徴である美しい海中景観や生物多様性の中心となっているのがサンゴである。
- サンゴが生息していない場所
-
 2020.10撮影
2020.10撮影
サンゴが生息していない場所では、生物相が貧弱となる。
サンゴは生態系のベースとなっている他にも、台風時に高波の力を弱める防波堤としての役割、骨格が細かくなり美しい砂浜を形成する役割がある。
また沖縄観光の最大の魅力の1つでもある。
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
ブセナ海中公園事業所
沖縄県名護市字喜瀬1744-1TEL.0980-52-3379FAX.0980-53-0675